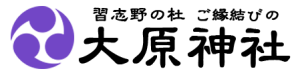【年中行事】
| 一月 | 歳旦祭 二十日 おびしゃ祭 |
| 二月 | 月並祭 三日 節分祭 (令和七年は二日) |
| 三月 | 月並祭 |
| 四月 | 月並祭 |
| 五月 | 月並祭 |
| 六月 | 月並祭 三十日 夏越しの祓い |
| 七月 | 月並祭 |
| 八月 | 月並祭 |
| 九月 | 月並祭 |
| 十月 | 月並祭 十九日 例大祭 |
| 十一月 | 月並祭 |
| 十二月 | 月並祭 三十一日 大祓式 |
| 丑年と未年にあたる年 | 七年大祭 |
歳旦祭

1月1日に行います。一年の始まりである新年を祝い、皇室の弥栄と国の益々の発展を祈るとともに、氏子崇敬者と地域社会の平和と繁栄を祈り元旦に行われるお祭りで、中祭にあたります。
御奉謝祭

1月20日に行います。昔から伝わる行事で、地域の五穀豊穣・家内安全・産業発展を願い、難を転ずるからとった南天の木でつくった弓矢を用い、鬼 鬼 鬼と書かれた的に弓を引き祈願します。より多くの的が当たった年ほど願いが叶うと言われています。参拝の方はどなたでも式にご参列いただき弓引きの儀にもご参加いただけます。
節分祭

2月3日に行います。昔から節分、豆撒きと慕われており、当社では節分祭として神事と豆撒きを行っております。
豆を撒く方を福の神、そのお手伝いをして下さる方々を福結芽(ふくむすめ・福の芽を結ぶ)と呼び、ご奉仕で福袋にお詰め頂いた福豆福菓子をご参詣のみなさまにお頒ちいたします。
夏越の祓え

6月30日に行います。一年を半分に分けた晦日(6月30日)前半の半年に知らず知らずに受けた穢れや過ちを祓い、残りの半年も無事に過ごせますようにと祓う神事です。当社では午前午後と一回ずつ執り行っています。お一人千円以上の玉串料を承っております。
例大祭

10月19日に行います。神社で毎年行われる祭祀のうち最も重要とされる祭典です。御氏子、崇敬者の安寧、五穀豊穣、発展などを祈念し執り行います。
※令和6年10月19日に、例大祭及び御創建九百年合同奉祝祭を齋行いたしました。
大祓式

12月31日に行います。
七年祭

各神社両親、親族等の役割があり大原神社は叔母にあたります。
二宮神社への昇殿順も役割順となっています。
数え年で七年に一度斎行されます。
令和三年丑年十月三十日に斎行されました。
室町時代 馬加(千葉市幕張)の城主であった千葉康胤公の奥方が懐妊し、11ヶ月経っても出産の気配がなく、心配した康胤公は二宮神社(三山村)、子安神社(畑村)、子守神社(馬加村)、三代王神社(武石村)の神職に命じて当時の馬加村の磯辺にて「磯出祭」を執行しました。
まもなく奥方は男子を安産し このご神徳に報いるため二宮神社を中心に安産御礼の大祭を執行することになりました。
実籾の大原神社では初日に二宮神社へ神輿を担ぎ参拝し、翌日花流しといい氏子地域を渡御します。まもなく奥方は男子を安産し このご神徳に報いるため二宮神社を中心に安産御礼の大祭を執行することになりました。
背中にみの文字の半纏を着た担ぎ手達の前後には祭りの所役や囃子連が並び祭りをより一層盛り上げます。
※令和三年の七年大祭は神事のみ行いました。 参考サイト
下総三山の七年祭り(ウィキペディア)
下総三山の七年祭り(習志野市ホームページ)